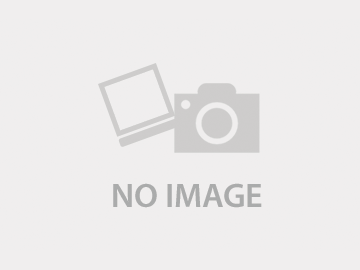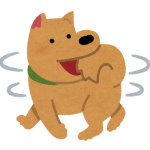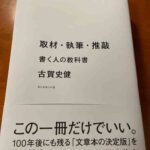街を歩いていると、最低賃金を引き上げようという看板を見かけた。
生活を守るためには必要だという声も多いし、確かにそういう面もあるとは思う。
でも、僕はどうしてもその一律の“正しさ”に、違和感を抱いてしまう。
なぜなら、あの頃の僕がいた世界には、最低時給も社会保険の強制も、今ほど厳しくなかったからこそ、今の自分があるからだ。
小規模な現場でしか得られない「本物の学び」
僕は最初から、大きな税理士法人に入りたいとは思っていなかった。
そこにある商流を見ても、将来の自分の姿は見えなかったからだ。
むしろ、小さな事務所で、全体を見渡しながら働きたい。
手の届く範囲で、手触りのある仕事を学びたかった。
でも、そういう事務所はどこもギリギリでやっていて、未経験者を時給1,000円以上で雇う余裕なんてなかった。
それでも僕は、どうしても入りたくて、時給は安くて構ようやくわないという形でようやく仕事を得た。
もし、あの頃の最低時給が今のように高かったら。
社会保険の加入義務が今のように厳しかったら。
僕はおそらく、入り口にも立てなかったと思う。
学びたい人が「違法」になる社会
最低賃金という制度が守ろうとしているのは、“今”の生活だ。
でも、僕が欲しかったのは、“未来”の可能性だった。
「時給900円でもいいから、現場で学びたい」
それが言えない社会は、学ぶ意欲のある人からチャンスを奪ってしまう社会でもある。
一律の制度が、育てる余白や受け入れる側の柔軟性を潰してしまう。
そして、結果として技術の継承も断たれていく。
「手を動かす」から見えてくるものがある
いまの僕は、AIも自動化もどんどん活用している。
でも、それでもたまに、あえて全部手書きで申告書を作ってみることがある。
意味があるかと問われれば、ないかもしれない。
けれど、手で書くからこそ、「あれ?この数字、どこかと合っていないな」と気づくこともある。
画面だけを見ていたら見落としてしまうような、些細だけれど重要な違和感。
「考える力」は、“考えるべきものを手で触ったことがある人”にしか生まれないと、僕は思っている。
自由競争に任せた方が、本質的な平等に近づく
もし時給が低すぎるなら、人は辞めていく。
誰も来ないなら、企業は時給を上げざるを得ない。
そうやって市場は自然に調整されていく。
一律で線を引くことが、すべての人のためになるとは限らない。
特に、これから何かを学びたいと思っている人、手に職をつけたいと思っている人にとっては、**その制度こそが“最大の参入障壁”**になってしまう。
自分のような人が、もう入って来られない社会になっていないか?
僕のように、
- 安い時給でも学ばせてほしいと願い、
- 泥臭く手を動かして覚え、
- 手探りで技術を身につけ、
- やがて自分のやり方で独立した人間が、今後は育ちにくくなるかもしれない。
制度が整えば整うほど、そこからこぼれ落ちる“意欲ある未熟者”が増えていく。
それは、本当に守るべき人を守れている制度なのだろうか。
僕は、あの頃の“未完成な自分”を社会が受け入れてくれたから、今がある。
だからこそ、制度の正しさよりも、育つ余白と挑戦の自由を大切にしてほしいと思っている。